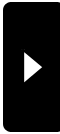スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2010年01月31日
こだわりの炭火料理
料理に使用している「ちくわ炭」を切る作業です。

炭は、2種類の料理で使います。
1つは、ほう葉味噌。
当館では、本物の ほう葉の上に焼き味噌をのせ、
炭火にて焼いて召し上がっていただきます。

2つ目は、飛騨牛のほう葉焼き
ほう葉の上に 飛騨牛ののせて焼きます。
勿論、炭火のコンロにて。

飛騨牛のほう葉焼き このお料理に関して、
直接、ほう葉と炭火を使用して 提供している所は、
私が知る限り旅館では「当館」だけでだと思います。
(万が一、ブログを御覧の方で、他でもやってる・・・と思われた方 ご連絡いただければと思います)
と言うのは、非常に手間がかかります。
料亭などでは、炭火の網焼き、または石焼などありますが、
敢えて、ほう葉にのせて(飛騨高山を代表する ほう葉 ですから )
)
この2種類の料理に使う 炭を 料理に合わせて切ります。
こちら↓↓は、ほう葉味噌用

そして、こちらが ↓↓↓ 飛騨牛のほう葉焼き用です。

厚さが違いますよ。
一旦 火が熾きると、火力を調整するには、なかなか難しいので、
炭の大きさで 使い分けております。
炭火 料理 なかなか 他では 味わえない料理だと思います
当館のこだわりの 炭でした

炭は、2種類の料理で使います。
1つは、ほう葉味噌。
当館では、本物の ほう葉の上に焼き味噌をのせ、
炭火にて焼いて召し上がっていただきます。
2つ目は、飛騨牛のほう葉焼き
ほう葉の上に 飛騨牛ののせて焼きます。
勿論、炭火のコンロにて。
飛騨牛のほう葉焼き このお料理に関して、
直接、ほう葉と炭火を使用して 提供している所は、
私が知る限り旅館では「当館」だけでだと思います。
(万が一、ブログを御覧の方で、他でもやってる・・・と思われた方 ご連絡いただければと思います)
と言うのは、非常に手間がかかります。
料亭などでは、炭火の網焼き、または石焼などありますが、
敢えて、ほう葉にのせて(飛騨高山を代表する ほう葉 ですから
 )
)この2種類の料理に使う 炭を 料理に合わせて切ります。
こちら↓↓は、ほう葉味噌用

そして、こちらが ↓↓↓ 飛騨牛のほう葉焼き用です。

厚さが違いますよ。
一旦 火が熾きると、火力を調整するには、なかなか難しいので、
炭の大きさで 使い分けております。
炭火 料理 なかなか 他では 味わえない料理だと思います

当館のこだわりの 炭でした

2010年01月30日
ビフォアー・アフター(華道編)
久し振りに、「ビフォアー・アフター」です
「ビフォアー・アフター」とは・・・・
かみなかブログで お伝えしている「ビフォアー・アフター」は、
生花です。
華道に通っている私の作品についてです。
華道教室にて、先生に手直ししていただいた 作品が 「ビフォアー」になります。
そして、「アフター」とは・・・・
華道教室にて、形を決めた 生花を、ばらして持ち帰り、
当館にて(玄関前or広間or廊下)にて 生けた 作品が「アフター」になるわけです。
ゆえに、「ビフォアー・アフター」
しかし、通常「ビフォアー・アフター」の場合、
アフターの方が 良くなるに決まっていますが、
かみなかブログに登場する、「ビフォアー・アフター」は そうなるとは限りません。
どんなに写真を撮ってきても、同じように生けても 同じものには ならないのです。
理由としては、
花器の違い。空間の違い。光の当たり具合の違い。そして・・・・腕の違い・・・
それでは、御覧ください。
「ビフォアー」

そして、玄関前に生けました「アフター」

木苺がポイントとなっております。
少し、動きをつけると格好よく映えるのですが、
玄関前に、同じように生けると、お客様に当たってします可能性があり、邪魔になるので、
木苺の角度を変えました。
それだけで、同じ花材でも雰囲気が ガラッと変わります。
ここにも華道の面白さ 奥深さがありますよ
奥深さがありますよ
「ビフォアー・アフター」 今後も、多々登場しますので、お楽しみに

「ビフォアー・アフター」とは・・・・
かみなかブログで お伝えしている「ビフォアー・アフター」は、
生花です。
華道に通っている私の作品についてです。
華道教室にて、先生に手直ししていただいた 作品が 「ビフォアー」になります。
そして、「アフター」とは・・・・
華道教室にて、形を決めた 生花を、ばらして持ち帰り、
当館にて(玄関前or広間or廊下)にて 生けた 作品が「アフター」になるわけです。
ゆえに、「ビフォアー・アフター」
しかし、通常「ビフォアー・アフター」の場合、
アフターの方が 良くなるに決まっていますが、
かみなかブログに登場する、「ビフォアー・アフター」は そうなるとは限りません。
どんなに写真を撮ってきても、同じように生けても 同じものには ならないのです。
理由としては、
花器の違い。空間の違い。光の当たり具合の違い。そして・・・・腕の違い・・・

それでは、御覧ください。
「ビフォアー」

そして、玄関前に生けました「アフター」

木苺がポイントとなっております。
少し、動きをつけると格好よく映えるのですが、
玄関前に、同じように生けると、お客様に当たってします可能性があり、邪魔になるので、
木苺の角度を変えました。
それだけで、同じ花材でも雰囲気が ガラッと変わります。
ここにも華道の面白さ
 奥深さがありますよ
奥深さがありますよ
「ビフォアー・アフター」 今後も、多々登場しますので、お楽しみに

Posted by 旅館かみなか at
11:52
│Comments(2)
2010年01月29日
冬の宮川沿い(鷺編)
昨日のブログに引き続き 宮川での遭遇です。
いつも 宮川では 鴨の群れをみますが、
んん?!
一瞬目を疑いました・・・・


鷺(サギ)?!
鷺も宮川には見られます。
しかし、下流の方で出会う率が高いのですが、
宮川朝市の辺りまで、来ちゃっていました・・・・・
この鷺。
遠くから見ると 鶴のように 品がありそうな・・・・
しかも、 日本舞踊にも 鷺を表現したものがありまして・・・
長唄 「鷺娘」 と言う、
非常に代表的な名曲があります。
(白鷺の精が町娘となってあらわれると言うストーリーの舞踊です。)
「長唄 鷺娘」 派手な部分としっとりとした部分が重なり合う名曲ですし、踊りも人気の演目の1つです。
舞踊の世界では、サギ=鷺娘=名曲
と言った構図で、古典中の古典であると同時に、格式の高いイメージを持っています。
そのような「鷺娘」のイメージが強いのに、
本物の鷺を見ると、
どことなく 悪者のイメージを抱いてしまいます。
近づくと 目の強さ。 鳴き声はハスキーボォイス。
(カラスの方が まだいい。と思っちゃうのは私だけでしょうか・・・)
鷺の場合 個体数の増加から寺社林に生息することが増え、
糞害や夜間の鳴き声などの問題が多くあります。
しかし、
鷺は、
水鳥の仲間ですから、宮川にいても おかしくはないのです。
個体数の増加の問題にしても 人間が原因だと思われるし・・・・
人間界と自然界・そして鳥達 上手く調和しててくれればと思った 宮川沿いでの風景でした
いつも 宮川では 鴨の群れをみますが、
んん?!
一瞬目を疑いました・・・・


鷺(サギ)?!
鷺も宮川には見られます。
しかし、下流の方で出会う率が高いのですが、
宮川朝市の辺りまで、来ちゃっていました・・・・・
この鷺。
遠くから見ると 鶴のように 品がありそうな・・・・

しかも、 日本舞踊にも 鷺を表現したものがありまして・・・
長唄 「鷺娘」 と言う、
非常に代表的な名曲があります。
(白鷺の精が町娘となってあらわれると言うストーリーの舞踊です。)
「長唄 鷺娘」 派手な部分としっとりとした部分が重なり合う名曲ですし、踊りも人気の演目の1つです。
舞踊の世界では、サギ=鷺娘=名曲
と言った構図で、古典中の古典であると同時に、格式の高いイメージを持っています。
そのような「鷺娘」のイメージが強いのに、
本物の鷺を見ると、
どことなく 悪者のイメージを抱いてしまいます。
近づくと 目の強さ。 鳴き声はハスキーボォイス。
(カラスの方が まだいい。と思っちゃうのは私だけでしょうか・・・)
鷺の場合 個体数の増加から寺社林に生息することが増え、
糞害や夜間の鳴き声などの問題が多くあります。
しかし、
鷺は、
水鳥の仲間ですから、宮川にいても おかしくはないのです。
個体数の増加の問題にしても 人間が原因だと思われるし・・・・
人間界と自然界・そして鳥達 上手く調和しててくれればと思った 宮川沿いでの風景でした

Posted by 旅館かみなか at
13:01
│Comments(0)
2010年01月28日
冬の宮川沿い(鴨編)
久し振りに、宮川沿いを歩いてみました。
日差しがありましたが、さすがリバーサイド
耳が痛くなるような 寒さでした。
(風があったからだと思われます)
雪解け水が 非常にきれいで透き通る 宮川

その中で、いつもの 群れを発見


冬場もいるんだ!? と第1印象。
え?! 寒くないのか?! 第2印象。
河川敷におりてみると、寄ってくるではないですか?!
午後4時近くだったので、冷え込みが次第に強まり、あまりゆっくりとすることができませんでした。
日中、日差しの出ている時には、宮川河川敷 オススメですよ
冬の冷たく 少し乾燥した 空気
を味わえます。
春夏秋冬 それぞれ 季節ごとに楽しめる 宮川河川敷でした。
その宮川にて いつもの群れ ではない モノを発見 明日お伝えします
明日お伝えします
日差しがありましたが、さすがリバーサイド

耳が痛くなるような 寒さでした。
(風があったからだと思われます)
雪解け水が 非常にきれいで透き通る 宮川


その中で、いつもの 群れを発見


冬場もいるんだ!? と第1印象。
え?! 寒くないのか?! 第2印象。
河川敷におりてみると、寄ってくるではないですか?!
午後4時近くだったので、冷え込みが次第に強まり、あまりゆっくりとすることができませんでした。
日中、日差しの出ている時には、宮川河川敷 オススメですよ

冬の冷たく 少し乾燥した 空気

を味わえます。
春夏秋冬 それぞれ 季節ごとに楽しめる 宮川河川敷でした。
その宮川にて いつもの群れ ではない モノを発見
 明日お伝えします
明日お伝えします
Posted by 旅館かみなか at
12:40
│Comments(0)
2010年01月27日
1週間後は節分
新年あけましておめでとうございます。とはじまり、
早くも1月も終盤です。
丁度1週間後には節分を迎えますね。
節分とは 季節を分ける事も意味します。
立春の前日にあたる 2月3日
この大寒から節分までの間、火の用心に十分注意するよう!
と言い伝えもあります。
節分は、季節・暦の上では、結構大きな行事だと 私は思っています。
その節分を1週間後に控え、
飛騨国分寺は いつものように 賑やかですよ

2月3日 は 国分寺にて 節分祭がひらかれます。
昨年復活した 鬼や七福神が、各家庭をまわる行事も行われる予定です。
当館にも来ますよ
その様子は、勿論ブログにてお伝えできると思います。
節分まで1週間です。
火の元には十分注意しましょう。
早くも1月も終盤です。
丁度1週間後には節分を迎えますね。
節分とは 季節を分ける事も意味します。
立春の前日にあたる 2月3日
この大寒から節分までの間、火の用心に十分注意するよう!
と言い伝えもあります。
節分は、季節・暦の上では、結構大きな行事だと 私は思っています。
その節分を1週間後に控え、
飛騨国分寺は いつものように 賑やかですよ

2月3日 は 国分寺にて 節分祭がひらかれます。
昨年復活した 鬼や七福神が、各家庭をまわる行事も行われる予定です。
当館にも来ますよ

その様子は、勿論ブログにてお伝えできると思います。
節分まで1週間です。
火の元には十分注意しましょう。
Posted by 旅館かみなか at
12:14
│Comments(0)
2010年01月26日
今年最初の華道にて
今年も、華道の様子を ブログにてお届けしていきます。
今年最初の華道では、
抹茶と茶菓子を頂きまして、華道開始です。


この抹茶茶碗 よく見ると 干支の「寅」ではないですか?!
興味深い 抹茶茶碗でした
さて、今年最初の 華道では このようになりました。

まだまだ寒い時期ですが、新春と言うように、春をイメージした感じです。
もうすぐ春が来ますよ
と表現してみました。
当館では、広間の床の間にて 飾ってあります。
ご宴会のお客様 ・ ご宿泊のお客様は 朝食時に
御覧いただけますよ
今年最初の華道では、
抹茶と茶菓子を頂きまして、華道開始です。


この抹茶茶碗 よく見ると 干支の「寅」ではないですか?!
興味深い 抹茶茶碗でした

さて、今年最初の 華道では このようになりました。

まだまだ寒い時期ですが、新春と言うように、春をイメージした感じです。
もうすぐ春が来ますよ

と表現してみました。
当館では、広間の床の間にて 飾ってあります。
ご宴会のお客様 ・ ご宿泊のお客様は 朝食時に
御覧いただけますよ

Posted by 旅館かみなか at
11:48
│Comments(0)
2010年01月25日
酒蔵めぐり(酒蔵公開)
第36回 「酒蔵めぐり」が開催されております。
(期間 2月28日まで)
市内6軒の造り酒屋が、一週間交替で酒蔵を公開しております。
無料ですし、予約も必要ありません。
いつも 見れない部分まで、この期間限定で 酒蔵を見学できます。
平田酒造さんからスタートした 酒蔵めぐり
今週は、
原田酒造さん にて 開催されておりますよ
期間:1月25日(月)~1月31日(日)
目印は この看板です。

※正午~午後1時の間は、お休みです。
参加者全員に記念盃をプレゼントしているそうです。
地酒の試飲もできますので、飛騨のお酒にふれあってみて下さい
(期間 2月28日まで)
市内6軒の造り酒屋が、一週間交替で酒蔵を公開しております。
無料ですし、予約も必要ありません。
いつも 見れない部分まで、この期間限定で 酒蔵を見学できます。
平田酒造さんからスタートした 酒蔵めぐり
今週は、
原田酒造さん にて 開催されておりますよ

期間:1月25日(月)~1月31日(日)
目印は この看板です。

※正午~午後1時の間は、お休みです。
参加者全員に記念盃をプレゼントしているそうです。
地酒の試飲もできますので、飛騨のお酒にふれあってみて下さい

2010年01月24日
二十四日市にて
飛騨高山 名物と言っていいでしょう。
二十四日市です。

旧暦の歳の市の名残りで毎年1月24日に開催します。
本町通り商店街にて開催されます。
昔は、農家の人たちが作った「しょうけ」「あみがさ」「おけ」等が、売られていました。
今尚、残っています。
しかし
最近では、ニーズに合わせて、色々なものが・・・・
歩行者天国のような感じですね。
しかし、その中で、昔ながらのブースを発見



出店の中で、バンドリや、笠を見ると 何か ホッとした気分がしました・・・・
本町1丁目~4丁目までの間で、3・4軒でしたが、 必ず残してもらいたい
二十四日市の風景です
この、
二十四日市 飛騨高山の 1月24日です。
今年を逃してしまった方、是非 来年 ご計画に
二十四日市です。

旧暦の歳の市の名残りで毎年1月24日に開催します。
本町通り商店街にて開催されます。
昔は、農家の人たちが作った「しょうけ」「あみがさ」「おけ」等が、売られていました。
今尚、残っています。
しかし
最近では、ニーズに合わせて、色々なものが・・・・
歩行者天国のような感じですね。
しかし、その中で、昔ながらのブースを発見




出店の中で、バンドリや、笠を見ると 何か ホッとした気分がしました・・・・

本町1丁目~4丁目までの間で、3・4軒でしたが、 必ず残してもらいたい
二十四日市の風景です

この、
二十四日市 飛騨高山の 1月24日です。
今年を逃してしまった方、是非 来年 ご計画に

2010年01月23日
三味のようかん
頂き物です。
まだ、試作段階と言うことを聞きまして。
(販売してあるのかもしれませんが・・・)
丹生川で作られた ようかんです。
3種類の味の詰め合わせですよ

ほうれんそう味&トマト味&かぼちゃ味
どれから食べようか 迷いますね。
3種類 食べてみました。
ほうれんそう味

トマト味

一番食べやすかったのが、かぼちゃ味です。(スイマセン かぼちゃようかんの画像がなくて・・・)
ほうれんそう味も 抹茶ぽくて 美味しかったです。
率直な意見ですと、少々寒天が強いかな~との印象を受けました。
しかし、100%丹生川産の食材です。
お土産等に お茶菓子に いかがでしょうか
まだ、試作段階と言うことを聞きまして。
(販売してあるのかもしれませんが・・・)
丹生川で作られた ようかんです。
3種類の味の詰め合わせですよ


ほうれんそう味&トマト味&かぼちゃ味
どれから食べようか 迷いますね。
3種類 食べてみました。
ほうれんそう味


トマト味


一番食べやすかったのが、かぼちゃ味です。(スイマセン かぼちゃようかんの画像がなくて・・・)
ほうれんそう味も 抹茶ぽくて 美味しかったです。
率直な意見ですと、少々寒天が強いかな~との印象を受けました。
しかし、100%丹生川産の食材です。
お土産等に お茶菓子に いかがでしょうか

Posted by 旅館かみなか at
13:01
│Comments(0)
2010年01月22日
ボケの花
久し振りに 花特集です。
この花は・・・・

梅・・・・???
梅ではありません。
ボケの花 と言います。
最初、この花の名を聞き 思ったのが、
梅が、こんなに早く咲くのかな~と感じました。
でも、梅じゃなくて、花が、ボケて 梅よりも早咲き の花なのか?!
春が来たと勘違いして 咲く花なのか・・・
と、非常に「ボケの花」にとっては 失礼な事を 思ってしまったのですが・・・・
そんな 「ボケの花」
薔薇科に属しております。
当館玄関正面にて 飾ってありますよ

個人的には、好きな花の1つにランクインしました
つぼみが膨らみ 開花するのが楽しみですし、
開花した花びらが、非常に綺麗です
寒さに強い「ボケの花」
この時期にはピッタリですよ
この花は・・・・
梅・・・・???
梅ではありません。
ボケの花 と言います。
最初、この花の名を聞き 思ったのが、
梅が、こんなに早く咲くのかな~と感じました。
でも、梅じゃなくて、花が、ボケて 梅よりも早咲き の花なのか?!
春が来たと勘違いして 咲く花なのか・・・
と、非常に「ボケの花」にとっては 失礼な事を 思ってしまったのですが・・・・
そんな 「ボケの花」

薔薇科に属しております。
当館玄関正面にて 飾ってありますよ

個人的には、好きな花の1つにランクインしました

つぼみが膨らみ 開花するのが楽しみですし、
開花した花びらが、非常に綺麗です

寒さに強い「ボケの花」

この時期にはピッタリですよ

Posted by 旅館かみなか at
12:58
│Comments(0)
2010年01月21日
客室が茶室にチェンジ
当館では、中庭に面したお部屋が 部屋ございます。
その1部屋 に 炉が切ってありまして・・・・
1年に1回 茶室に変化するわけです。
客室なのに・・・
こうなりました ↓↓↓

ちょうど 外は日差しがありまして 明るく撮れました。
1年に1回だけしか 見ることのできない 茶室。

床の間 も お茶席用にと 寅の香合等 飾ってありますよ

この香合は 小糸焼きになります。
このように、当館では、ご宿泊・ご宴会・ そしてお茶会にご利用いただけますよ
もし、お茶会等 ご予定のお客様 当館で承っております。
1月中旬~下旬の ご利用と制限はありますが、
詳細等、お気軽にご相談・お問い合わせくださればありがたいです
お待ちしております。
その1部屋 に 炉が切ってありまして・・・・
1年に1回 茶室に変化するわけです。
客室なのに・・・
こうなりました ↓↓↓
ちょうど 外は日差しがありまして 明るく撮れました。
1年に1回だけしか 見ることのできない 茶室。
床の間 も お茶席用にと 寅の香合等 飾ってありますよ

この香合は 小糸焼きになります。
このように、当館では、ご宿泊・ご宴会・ そしてお茶会にご利用いただけますよ

もし、お茶会等 ご予定のお客様 当館で承っております。
1月中旬~下旬の ご利用と制限はありますが、
詳細等、お気軽にご相談・お問い合わせくださればありがたいです

お待ちしております。
2010年01月20日
廊下に特設つくばい
お茶席に 入る前に 手を清める 手水鉢があります。
通常、お茶席は外から 入りますから、
茶庭の手水鉢を使います。
当館では、2階の客室がお茶席になりますので、
特設の つくばいを作ります。
つくばいとは??
(つくばい(蹲)とは、茶道の習わしによりお客様が這いつくばるようにして、
手を洗う事から つくばい と言われるようになりました)
廊下に 特設に作った つくばいです

竹等も 手作りですよ

とても 良い雰囲気だったので、いつもこの状態にしておきたいと思うところでしたが・・・・
さて明日は いよいよ 茶室に入りましょう

Posted by 旅館かみなか at
12:16
│Comments(0)
2010年01月19日
お茶席用の炭
当館で お茶会が開かれました。
その模様を 少しだけお伝えしたいと思いまして・・・
昨日から始まった「お茶会シリーズ」 です。
水屋を少し覗いて見ました。
(水屋とは・・・
茶会等の準備や後始末する所になります。通常、茶室の隅に設けたり、隣室に設けます。
水屋も 客室を使用しています)
そこで 発見したもの
「炭」です

お茶会用の炭 これが本当の 「炭」と言うものです。
「炭」と一言にいっても、いろいろな種類・形があります。
料理に使用する炭火焼き用の炭は、火が早く熾るようにと、当館では「ちくわ炭」を使用しています。
その場、その場に適した 「炭」を 用意していますが、
お茶席用の「炭」 立派なものでした
炭による 消臭等 いろいろな分野で 炭製品を見られますが、
この「炭」 お部屋の片隅に 置いていても 格好がつく「炭」です
ご宿泊のお客様 こちらの 「炭」 ご希望でしたら、
ご用意いたしますので、お問い合わせ下さい。
その模様を 少しだけお伝えしたいと思いまして・・・
昨日から始まった「お茶会シリーズ」 です。
水屋を少し覗いて見ました。
(水屋とは・・・
茶会等の準備や後始末する所になります。通常、茶室の隅に設けたり、隣室に設けます。
水屋も 客室を使用しています)
そこで 発見したもの

「炭」です
お茶会用の炭 これが本当の 「炭」と言うものです。
「炭」と一言にいっても、いろいろな種類・形があります。
料理に使用する炭火焼き用の炭は、火が早く熾るようにと、当館では「ちくわ炭」を使用しています。
その場、その場に適した 「炭」を 用意していますが、
お茶席用の「炭」 立派なものでした

炭による 消臭等 いろいろな分野で 炭製品を見られますが、
この「炭」 お部屋の片隅に 置いていても 格好がつく「炭」です

ご宿泊のお客様 こちらの 「炭」 ご希望でしたら、
ご用意いたしますので、お問い合わせ下さい。
Posted by 旅館かみなか at
11:50
│Comments(0)
2010年01月18日
干支の和菓子
当館では、茶会席(茶懐石)も承っております。
(本格的な茶懐石となりますと、料理も完全にかわります。
今回は茶会席とさせていただきました。 当館で お茶席 そして 通常のご宴会コース になっております)
今週のブログは 茶会席に関連する内容が多いと思いますので、
またかよ!? と思わず、御覧になっていただければ ありがたいです
干支を連想させた 和菓子です。

今年は「寅」 虎のしま模様です。
抹茶茶碗は、初釜にふさわしい 松と竹です。
おめでたい感じの 抹茶茶碗。
抹茶と お菓子 の 紹介をしても 何??? という感じですが、
まずは、お茶 と 和菓子で 茶会の雰囲気を
(本格的な茶懐石となりますと、料理も完全にかわります。
今回は茶会席とさせていただきました。 当館で お茶席 そして 通常のご宴会コース になっております)
今週のブログは 茶会席に関連する内容が多いと思いますので、
またかよ!? と思わず、御覧になっていただければ ありがたいです

干支を連想させた 和菓子です。
今年は「寅」 虎のしま模様です。
抹茶茶碗は、初釜にふさわしい 松と竹です。
おめでたい感じの 抹茶茶碗。
抹茶と お菓子 の 紹介をしても 何??? という感じですが、
まずは、お茶 と 和菓子で 茶会の雰囲気を

Posted by 旅館かみなか at
11:48
│Comments(0)
2010年01月17日
飛騨の里ライトアップ
今年初めての 観光情報をお伝えします。
ブログの見出しには・・・・
当館情報を始め高山市内の観光情報を・・・
なんて記載したありますが、ほぼ関係の内容でした。
しかし! 本日は 観光情報です。
「飛騨の里 冬の白銀ライトアップ 」
1月16日(土)~2月28日(日) 午後5時30分~午後9時

冬の夜に浮かぶ上がる 飛騨の里
これまた幻想的です。
どうぞ御覧下さい
マイカーでないお客様は、濃飛バスをご利用下さい。
ブログの見出しには・・・・
当館情報を始め高山市内の観光情報を・・・
なんて記載したありますが、ほぼ関係の内容でした。
しかし! 本日は 観光情報です。
「飛騨の里 冬の白銀ライトアップ 」
1月16日(土)~2月28日(日) 午後5時30分~午後9時

冬の夜に浮かぶ上がる 飛騨の里
これまた幻想的です。
どうぞ御覧下さい

マイカーでないお客様は、濃飛バスをご利用下さい。
2010年01月16日
特製「飛龍頭」(完成版)
昨日ブログにてご紹介しました 特製「飛龍頭」(工程編)に
引き続きまして、完成版をお伝えしたいと思います。
ダシ汁の中に 昨日揚げた 「飛龍頭」を 入れ軽く煮込みます。
色添えに 大根&人参も ダシ汁にて煮込みます。
そして 完成したのが こちら ↓↓↓

 当館 特製 「飛龍頭」
当館 特製 「飛龍頭」
何故、ここまで 「飛龍頭」にこだわるのか?!
1つは、当館料理長 得意料理の1つであるのと同時に、
もう1度、 「飛龍頭」 を 正しく理解していただきかかった・・・との想いが強くて・・・
と言うのも、 「飛龍頭」=「がんもどき」
コンビニのおでんコーナー等で、気軽に目にする事ができます。
そうなると、当館に限らず、
日本料理店などで 「飛龍頭」が出てきた時に、思うのが・・・・
「なんや~ がんもどきか~」
となってしまいがちです
確かに、見た目には、さほど変化がないため そのような
第一印象になってしまうのが寂しいですが・・・
日本料理の代表的な 練り物の1つ
手間と時間がかかった 「飛龍頭」 だ!
と言うことを、このブログを通して、頭の隅にでも 入れておいてもらえばありがたいと思います。
そして何より
精進料理 または、日本料理店 で「飛龍頭」と出合った時は、
「なんだ!がんもどきか~」ではなく!
「お! 中身は何かな~?」と少しだけ
興味をもっていただけると、嬉しいです。
そして
当館の
一味違う「飛龍頭」 もお楽しみいただければ幸いです
引き続きまして、完成版をお伝えしたいと思います。
ダシ汁の中に 昨日揚げた 「飛龍頭」を 入れ軽く煮込みます。
色添えに 大根&人参も ダシ汁にて煮込みます。
そして 完成したのが こちら ↓↓↓
 当館 特製 「飛龍頭」
当館 特製 「飛龍頭」
何故、ここまで 「飛龍頭」にこだわるのか?!
1つは、当館料理長 得意料理の1つであるのと同時に、
もう1度、 「飛龍頭」 を 正しく理解していただきかかった・・・との想いが強くて・・・
と言うのも、 「飛龍頭」=「がんもどき」
コンビニのおでんコーナー等で、気軽に目にする事ができます。
そうなると、当館に限らず、
日本料理店などで 「飛龍頭」が出てきた時に、思うのが・・・・
「なんや~ がんもどきか~」
となってしまいがちです

確かに、見た目には、さほど変化がないため そのような
第一印象になってしまうのが寂しいですが・・・
日本料理の代表的な 練り物の1つ
手間と時間がかかった 「飛龍頭」 だ!
と言うことを、このブログを通して、頭の隅にでも 入れておいてもらえばありがたいと思います。
そして何より
精進料理 または、日本料理店 で「飛龍頭」と出合った時は、
「なんだ!がんもどきか~」ではなく!
「お! 中身は何かな~?」と少しだけ
興味をもっていただけると、嬉しいです。
そして
当館の
一味違う「飛龍頭」 もお楽しみいただければ幸いです

Posted by 旅館かみなか at
11:18
│Comments(2)
2010年01月15日
特製「飛龍頭」(工程編)
当館、料理長の得意料理の1つをご紹介。
タイトルにあるよう「飛龍頭」(ひりょうず)
調べてみたところによりますと、
関西方面での呼び方のようです。
関東方面ですと、「がんもどき」と呼ばれています。
「がんもどき」と呼んだほうが、親しみがあると思いますが、
今回は「飛龍頭」とさせていただきます。
豆腐をすり鉢にて すり、色々な具材をあわせていきます。
この する感覚が難しいです。
当館の「飛龍頭」は、甘海老&百合根&銀杏&きくらげ&大和芋
うまく混ざったところで、適当な大きさに形を作ります。

そして、揚げます。 この揚げる時が、一番神経を使いますよ
特に油の温度です。

そして、完成して揚がりました。

これだけで、食べても非常に美味しいですが、
お客様にお出しする時は、
ダシの中で、煮込みます。
この工程だけも、「飛龍頭」 非常に手間と時間がかかる料理の1つです。
明日は、完成版として 「飛龍頭」について、
ブログにてご紹介しようと思います。
何故、「飛龍頭」にこだわるのか?!
やはり、料理長の得意料理の1つであるのと同時に、
折角ですので、私の「飛龍頭」に対する思いもお伝えしたいと思いまして・・・・
明日をお楽しみに
タイトルにあるよう「飛龍頭」(ひりょうず)
調べてみたところによりますと、
関西方面での呼び方のようです。
関東方面ですと、「がんもどき」と呼ばれています。
「がんもどき」と呼んだほうが、親しみがあると思いますが、
今回は「飛龍頭」とさせていただきます。
豆腐をすり鉢にて すり、色々な具材をあわせていきます。
この する感覚が難しいです。
当館の「飛龍頭」は、甘海老&百合根&銀杏&きくらげ&大和芋
うまく混ざったところで、適当な大きさに形を作ります。

そして、揚げます。 この揚げる時が、一番神経を使いますよ

特に油の温度です。

そして、完成して揚がりました。

これだけで、食べても非常に美味しいですが、
お客様にお出しする時は、
ダシの中で、煮込みます。
この工程だけも、「飛龍頭」 非常に手間と時間がかかる料理の1つです。
明日は、完成版として 「飛龍頭」について、
ブログにてご紹介しようと思います。
何故、「飛龍頭」にこだわるのか?!
やはり、料理長の得意料理の1つであるのと同時に、
折角ですので、私の「飛龍頭」に対する思いもお伝えしたいと思いまして・・・・

明日をお楽しみに

2010年01月14日
お祝いに どうぞ♪
当館でのご宴会を始め ご宿泊の お客様にも ご要望がありましたら、
心ばかしの サービスをしております。
例えば、先日ご宴会のお客様より米寿のお祝いと言うことをお聞きしておりました。
特別なサービスはできませんが、
折角のお祝いの席に 当館を選んでいただいた気持ちを込めまして、
「お赤飯」をお料理のコースに追加。

勿論、こちらはサービスです。
もし、記念日・または、還暦をはじめ、喜寿・米寿などのお祝い事 これから増えてくると思います。
ご予約の際、一声お申し付けくださると、事前に対応できますので、
御遠慮なさらず、お申し付け下さい
心ばかしの サービスをしております。
例えば、先日ご宴会のお客様より米寿のお祝いと言うことをお聞きしておりました。
特別なサービスはできませんが、
折角のお祝いの席に 当館を選んでいただいた気持ちを込めまして、
「お赤飯」をお料理のコースに追加。
勿論、こちらはサービスです。
もし、記念日・または、還暦をはじめ、喜寿・米寿などのお祝い事 これから増えてくると思います。
ご予約の際、一声お申し付けくださると、事前に対応できますので、
御遠慮なさらず、お申し付け下さい

2010年01月13日
特製 焼肉のタレ
以前にも ブログにてご紹介しました 飛騨牛につけて召し上がる
当館特製の「焼肉のたれ」
今回は、いつもより少し多めに製作。
ごまを練るところから始まります。

そして、順に 砂糖&酒&醤油&しょうが 等を入れながら すります。

そして 完成したのが こちら↓↓

当館特製のたれになります。
ゴマたれになるので、ゴマが苦手なお客様には、おろしポン酢たれをご用意しております。
何なりとお申し付け下さい。
飛騨牛の本来の肉の味を堪能するには、塩 が一番ではありますが、
やっぱり タレにつけて食する事をオススメします。
そうなると、タレの味で、飛騨牛の味を殺すことも 生かす事もできちゃうわけで・・・
飛騨牛の陶板焼きのメニューの中では一番重要になってくる 当館特製のタレのご紹介でした
当館特製の「焼肉のたれ」
今回は、いつもより少し多めに製作。
ごまを練るところから始まります。

そして、順に 砂糖&酒&醤油&しょうが 等を入れながら すります。

そして 完成したのが こちら↓↓


当館特製のたれになります。
ゴマたれになるので、ゴマが苦手なお客様には、おろしポン酢たれをご用意しております。
何なりとお申し付け下さい。
飛騨牛の本来の肉の味を堪能するには、塩 が一番ではありますが、
やっぱり タレにつけて食する事をオススメします。
そうなると、タレの味で、飛騨牛の味を殺すことも 生かす事もできちゃうわけで・・・
飛騨牛の陶板焼きのメニューの中では一番重要になってくる 当館特製のタレのご紹介でした

Posted by 旅館かみなか at
13:10
│Comments(0)
2010年01月12日
珍しい松ボックリ
松というと お正月にはかかせない木の1つです。
門松をはじめ、松飾り、そしてお料理の盛り付けにも 松の枝で飾りをつくるなど、
1月には、かかせない松。
そんな 松ですが・・・
珍しい松ボックリを発見

長さ10センチ、太さ5センチ、レモンほどの大きさです。
松ボックリから松が出てるわけじゃなく、松に付いた松ボックリなんだと思います。
小さい頃に四葉のクローバーを見つけると、
ものすごく幸せな気分になりました。
なんだか、それと同じようで、
1月に この松ボックリを発見した事で、
小さな幸せを感じたひと時でした
門松をはじめ、松飾り、そしてお料理の盛り付けにも 松の枝で飾りをつくるなど、
1月には、かかせない松。
そんな 松ですが・・・
珍しい松ボックリを発見


長さ10センチ、太さ5センチ、レモンほどの大きさです。
松ボックリから松が出てるわけじゃなく、松に付いた松ボックリなんだと思います。
小さい頃に四葉のクローバーを見つけると、
ものすごく幸せな気分になりました。
なんだか、それと同じようで、
1月に この松ボックリを発見した事で、
小さな幸せを感じたひと時でした

Posted by 旅館かみなか at
11:39
│Comments(0)